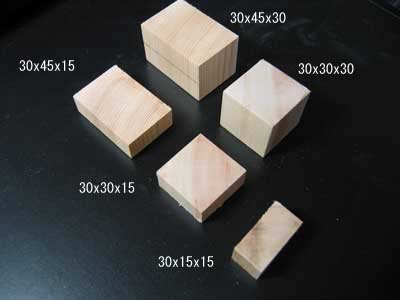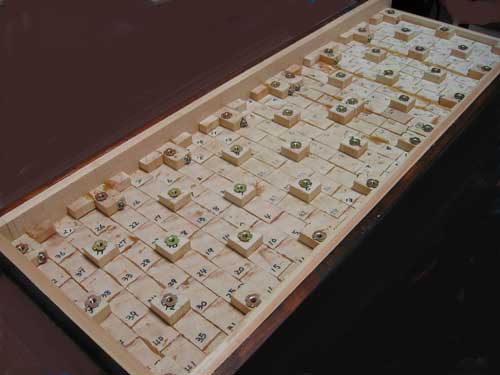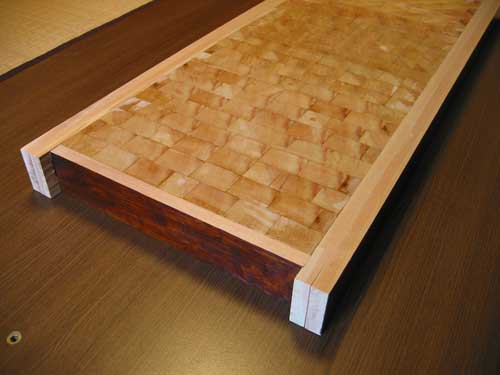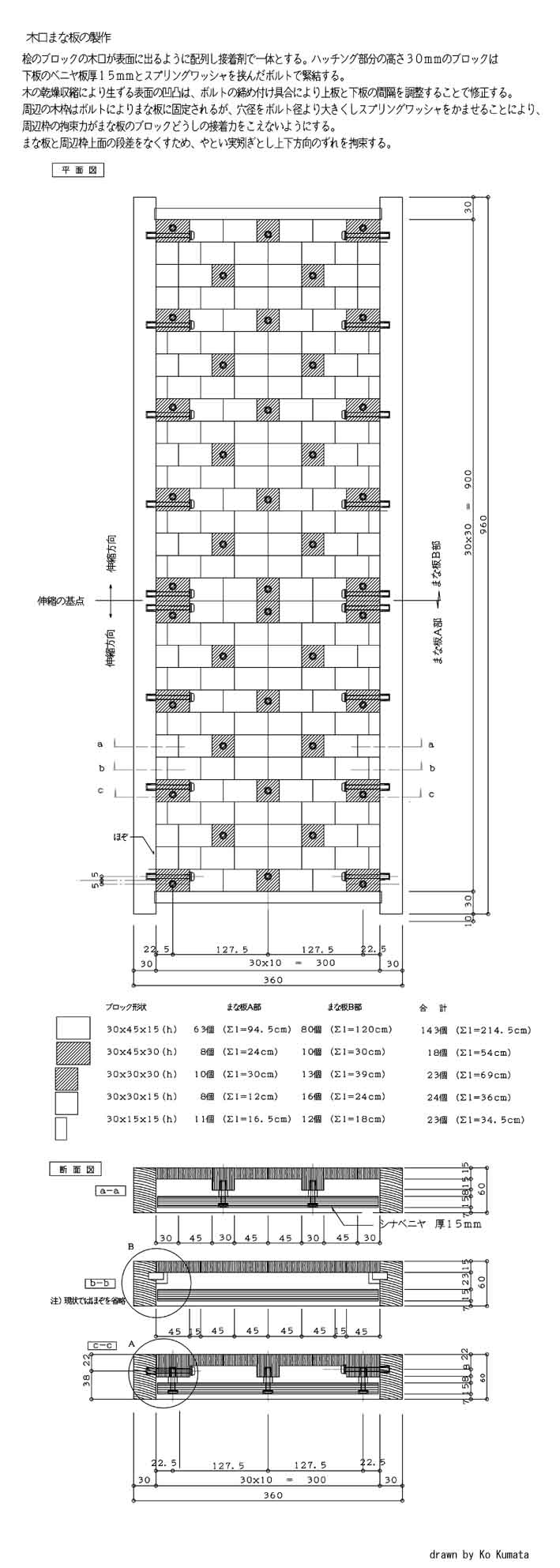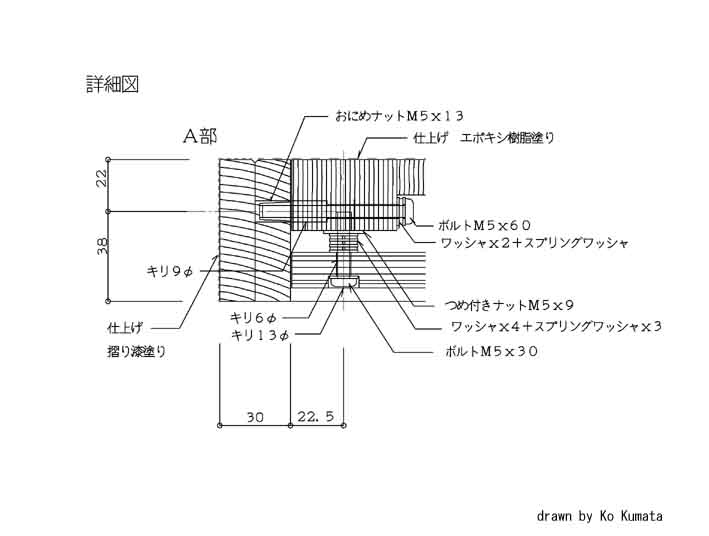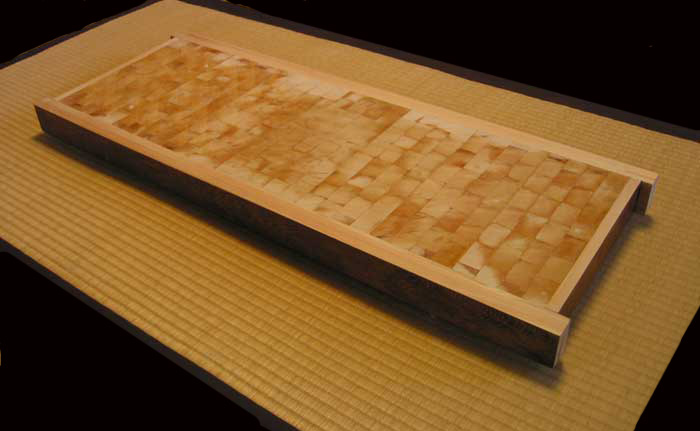木口まな板(完成したところ)
7月から製作にかかり、8月7日についに完成。
途中、本業の仕事が入ったため、一時中断。
実働3週間、延べ時間で75時間くらい。
・サイコロ切断 30時間
・サイコロを並べて板にする 15時間
・周辺枠作り(漆塗りも含め) 20時間
・組み立て、調整 10時間

| ブロックの製作 |
|
30x30x900、30x45x900の桧の角材を鋸でブロック状に切断してみたが、試験的に並べてみたところ、材の断面が正四角形でなく菱形であることが分かった。
|
中ブロックの製作
|
小ブロックを組み合わせて中ブロックを作成する。
|
 |
中ブロックの上面の状態 |
|
|
 |
中ブロック4個をまとめて右半分(B部)がほぼ完成 |
|
表面には目地の空隙を埋めるためエポキシ樹脂を鏝で塗りこんだ。
|
上面のクローズアップ
|
木目が寄木細工のような効果を出している。
|
 |
同裏面 |
|
|
 |
裏面に金物を取り付ける |
|
まな板に側板を取り付けるボルトとつめ付きナット。
|
 |
裏面全体 |
|
|
 |
金物(オニメナットとつめ付きナット) |
|
|
 |
金物(つめ付きナットとボルト、ワッシャの組み合わせ) |
|
この金物がまな板面を平らに保つ新兵器である。
|
 |
裏板を上記のボルトで取り付ける |
|
このボルトの締め具合により、まな板と裏板の間隔を調整できる。
|
 |
まな板と裏板の間のワッシャ |
|
この状態でボルトを緩めるとスプリングワッシャが、まな板と裏板を2.5mmまで押し広げる。裏板はまな板とボルトで接合されているだけで、側板には拘束されていない。
|
 |
組み立て完了した木口まな板の細部 |
|
側板の摺り漆仕上げは色むらがあり、師匠のKさんからはNGが出た。
|
 |
麺帯ストッパーとほぞ穴 |
|
そばMLのdeerhunterさんのアイデアである、たたんだ麺帯の左右を逆にして左側に、麺帯と同じ厚みのストッパーをつけるという案を頂いた。
|
 |
完成図 |
|
|
図面集(1)
|
平面図、断面図
|
 |
図面集(2) |
|
詳細図
|
 |
木口まな板製作後7ヶ月 |
|
木口まな板は製作後、しばらくしてから暴れだす(狂いが生じる)例が多いといわれてます。私の木口まな板も作ってから半年以上経過しました。
|
 |
|
|
|