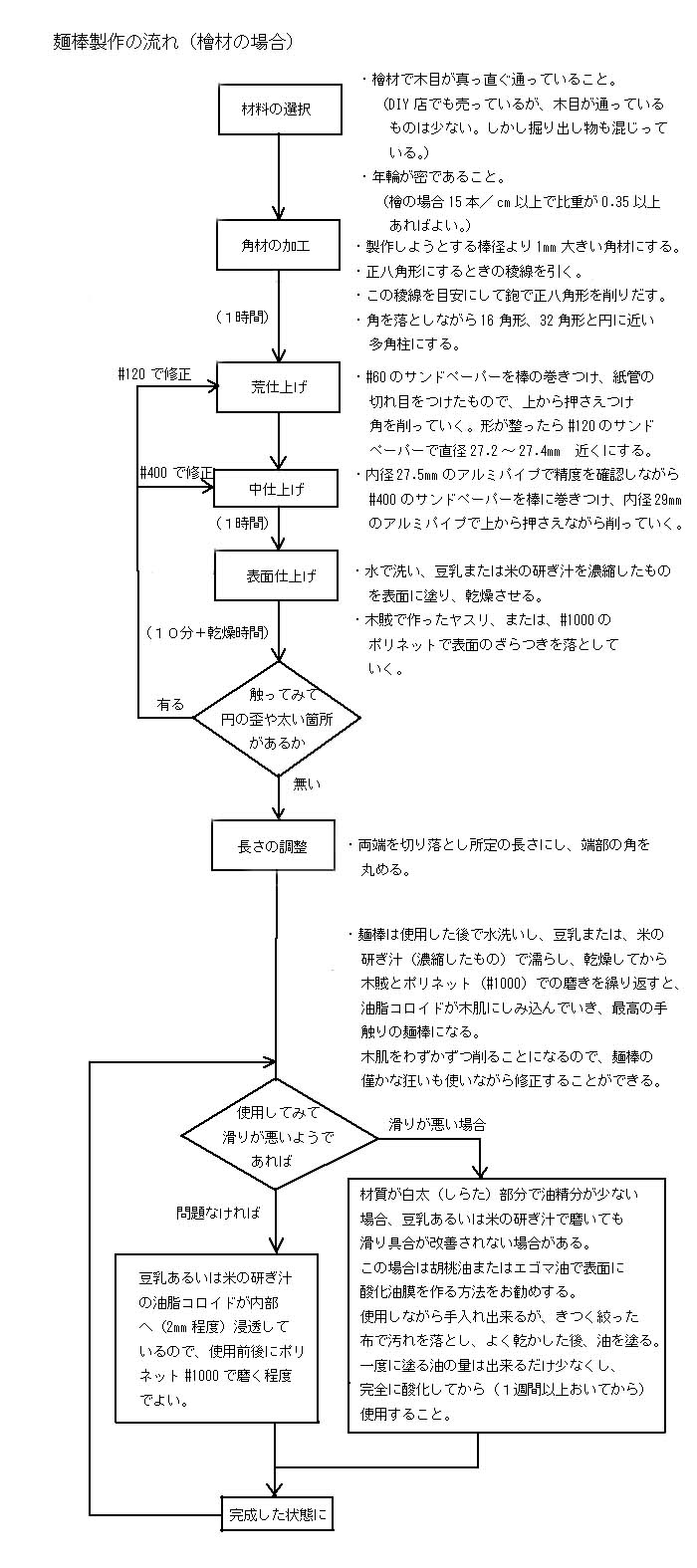麺棒製作教室 (延し棒)
1.材料、工具等準備するもの
1)檜角材 28mmX28mmx90cm 以上
2)作業台 参照
3)鉋(平鉋) 参照
4)鋸
5)サンドペーパー、ポリネット
#60(1枚)、#150(1枚)、#400(1枚)、
#600(1枚)、マイクロポリネット#1000(1枚)
6)紙筒(内径35mm程度、L=20cm)
7)アルミパイプ2本(内径27.5mm、29mm ,L=12.5cm) パイプの加工
8)木賊ヤスリ 木賊ヤスリの作り方
9)豆乳 又は濃縮した米の研ぎ汁
10)ノギス(10cm程度、1000円以下)、ハサミ
11)ボロ切れ(タオル等、麺棒を傷つけないために用いる。)
12)マスク(サンディングで木の粉が飛びます)、軍手
2.麺棒製作工程のあらまし

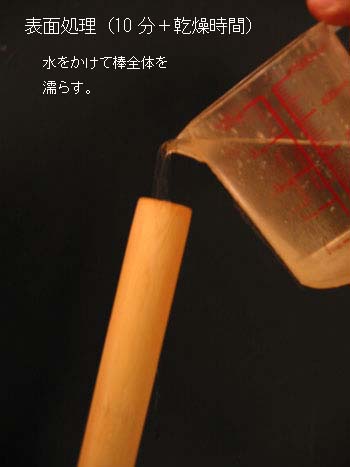
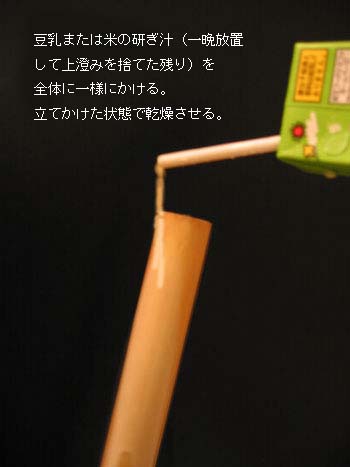
3.各段階の写真説明



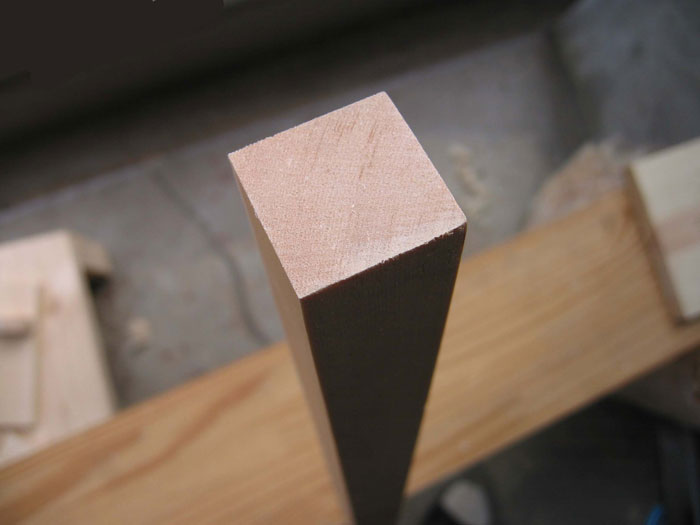










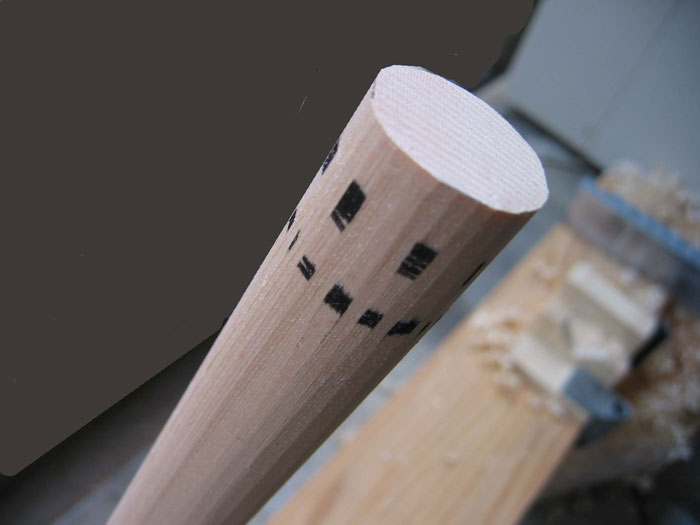

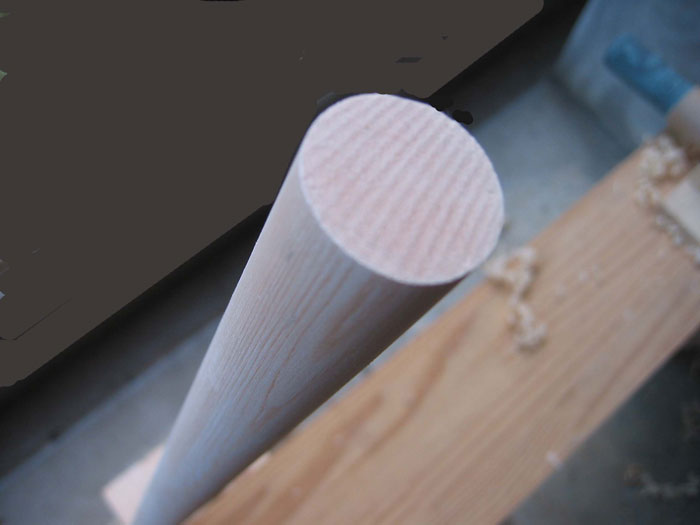








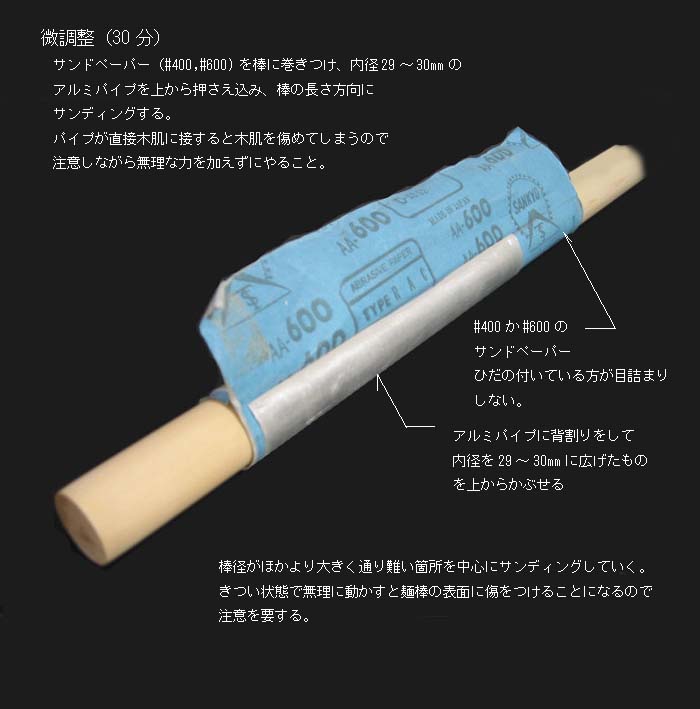
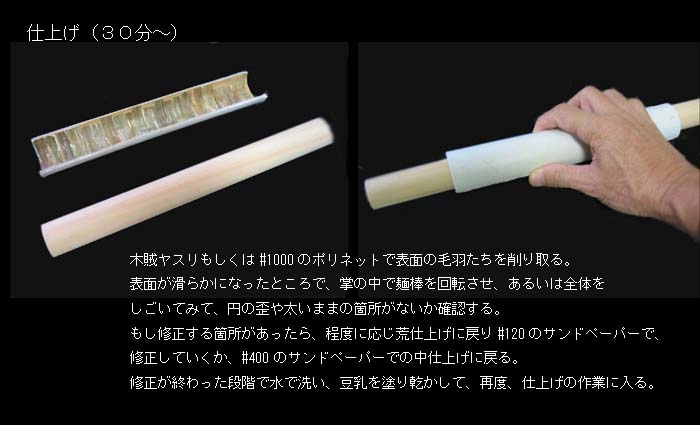
長さ80cm,太さ27mmの檜の延し棒の製作にチャレンジします。
経験のない人でも、1日ですぐに使用できる延し棒ができるように手順を考えました。
初心者が勘に頼った方法で製作を行うと、なかなか期待どうりのものが作れません。
工具、冶具の力を借りて行ったほうがより簡単に、精度の高いものが作れます。